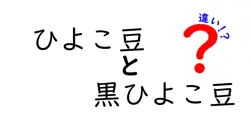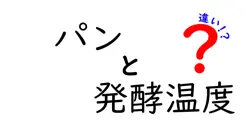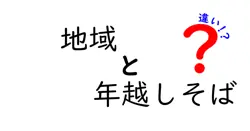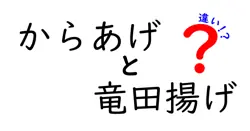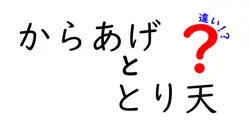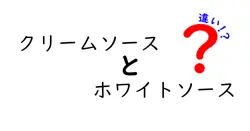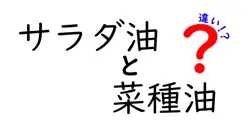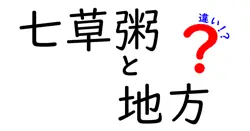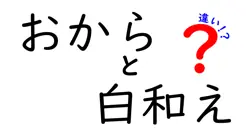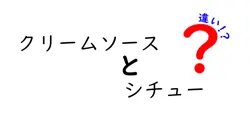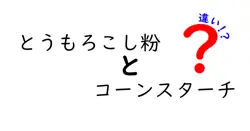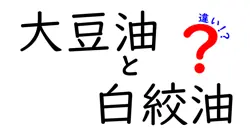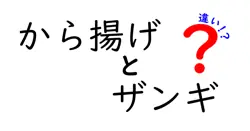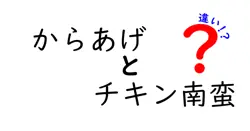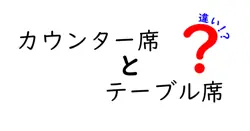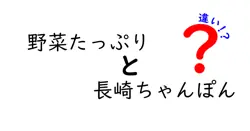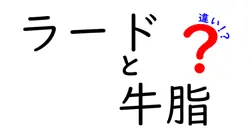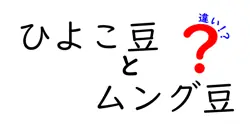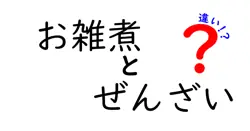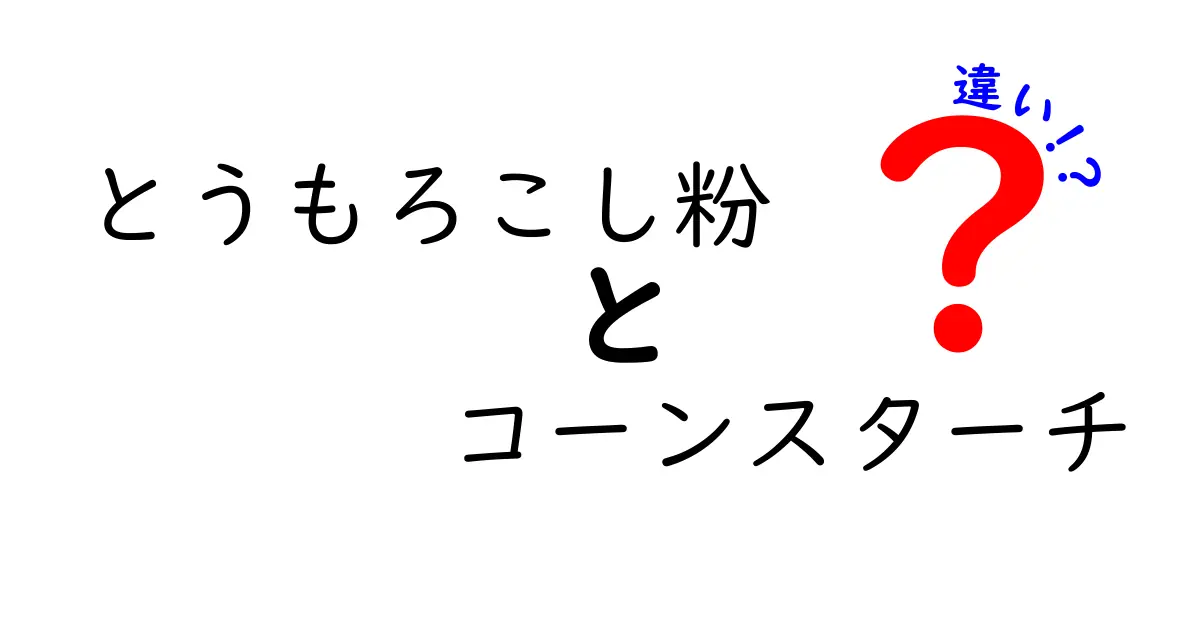

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
とうもろこし粉とコーンスターチの基本的な違いを知ろう
ここでは「とうもろこし粉」と「コーンスターチ」がどう違うのか、原料や成分、使い道、作り方の違いをやさしく説明します。
まず大きなポイントは三つです。1つ目は成分の違い。とうもろこし粉は玉蜀黍の粒を粉砕してできる粉全体を指します。つまりデンプンだけでなく、微量のたんぱく質や脂肪、食物繊維まで含み、色や風味もより複雑です。コーンスターチはその名の通り、コーンから抽出して取り出された澱粉だけを集めたものです。つまりほぼ純粋なデンプンで、水分を含むと粘りが強くなる性質があります。
2つ目は粘度の違い。料理でとろみを付けるとき、コーンスターチは水分と混ぜて熱を加えると粘りが出やすく、ソースやスープに最適です。対してとうもろこし粉は粉そのものの性質を活かし、生地づくりや風味づけに向くことが多く、粘りは控えめです。
3つ目は用途の違い。粉はパンやクッキー、ケーキなどの材料になり、スターチはソースのとろみづけや衣の粘着性向上などに使われます。以下で詳しく見ていきましょう。
コーンスターチの詳しい特徴とどう選ぶか
では具体的にどんな場面で使い分けるのかを見ていきます。コーンスターチはとろみづけの王道として、スープ・シチュー・カスタード系のデザート・ソースで活躍します。水と混ぜてから鍋に入れるとダマになりにくく、加熱中は静かに混ぜ続けると均一なとろみが付きます。熱を過剰に加えすぎると過度に硬くなることがあるので、仕上がりの粘度を見ながら少しずつ加えるのがコツです。注意点としては冷えると粘度が変化する点。冷めると少し硬くなることがあるので、ソースを冷まして提供する場合は水分量を少し多めに見積もると良いでしょう。
一方、とうもろこし粉は焼き菓子の生地作りや風味づけ、パンづくりなどに向いています。デンプンが多い分、焼き上がりのふくらみや口あたりに影響します。
これら三つのポイントを覚えると、買い物や料理の際にどちらを使えばよいか迷う回数がぐんと減ります。
まとめとしては、使い分けのコツはとろみの出方・風味・焼き上がりの食感の三点を意識することです。必要に応じて組み合わせるレシピも多いので、まずはレシピの指示を読み、必要な粘度と風味をイメージしてみましょう。
友達と台所で実験をしていた日のこと。コーンスターチを小さじ一杯だけ水で溶かして鍋に入れると、一瞬でスープが透明からとろりと粘る姿にみんなで驚いた。私は思わず『これがデンプンの力だね』とつぶやき、友達は『でもコーンスターチだけだと風味が薄いから、違う粉と混ぜて使うと面白いね』と話しました。その後、とうもろこし粉を加えて焼くパンの実験をしたところ、焼き色と香りが変わり、ふんわり感が出ることを発見。こんな日常の小さな観察が、料理の世界の「違い」を楽しく学ぶきっかけになります。