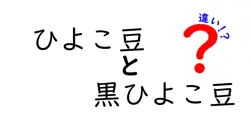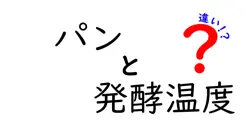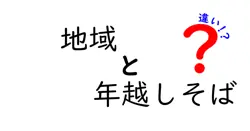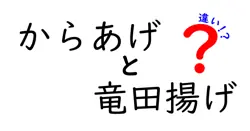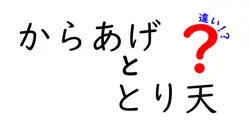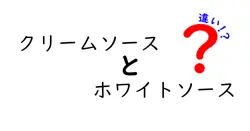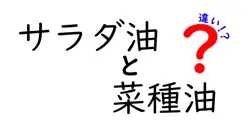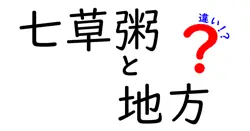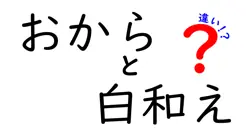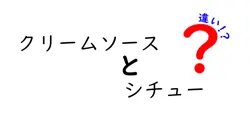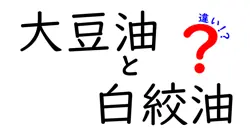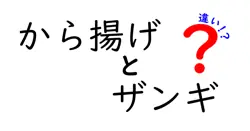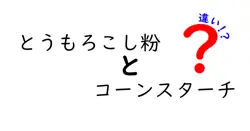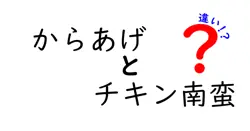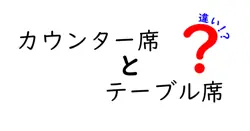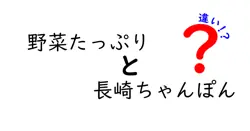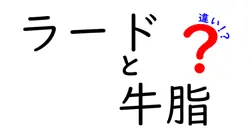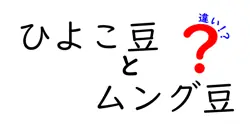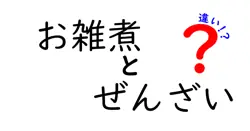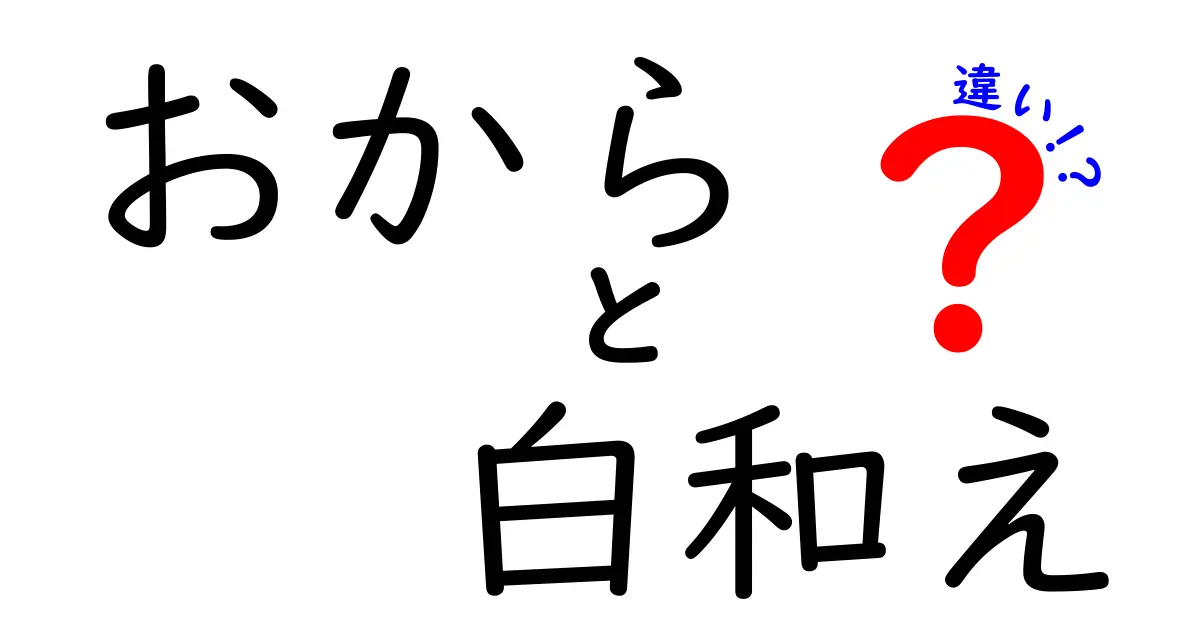

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
おからと白和えの違いを理解する
おからとは何かを知ることから始めましょう。
おからは大豆を絞って豆乳を作ったときに残る“絞りかす”のことです。
つまり、豆乳を作る工程で生まれる副産物の一つで、食物繊維が多く、タンパク質も少しだけ含んでいます。
この性質から、料理の中で主役になることよりも、脇役として素材の栄養と食感をプラスする役割を担うことが多いのです。
白い色をしていて、崩れやすい独特の柔らかさがあります。
味は比較的淡く、味付けをしっかりする料理の土台にも、薄味で素材の風味を生かすレシピにも使いやすい特徴があります。
一方、白和えとはどういう料理なのかを見てみましょう。
白和えは豆腐を主材料にして、すりごまや味噌、砂糖などを混ぜた和え衣で野菜やきのこなどと和える、日本の伝統的な料理のひとつです。
白和えは「和える」ことで味が一体化し、野菜の瑞々しさと豆腐のクリーミーさが組み合わさるのが魅力です。
おからと白和えは、材料も使い方も大きく異なりますが、どちらも日本の食卓でよく見かける食品です。
ここからは、なぜこの二つを混同しやすいのか、そして具体的にどう違うのかを、わかりやすく整理していきます。
重要ポイントを押さえるだけで、理解がぐんと深まります。
まずは基本の違いをまとめると、原材料、食感、用途、栄養価、保存方法がそれぞれ異なる点が大きな特徴です。
おからは“素材そのもの”の性質を活かして、サラダや炒め物、煮物、卵焼き風の具材など、幅広い料理に混ぜ込むことができます。
一方の白和えは、主に野菜と豆腐を和える“完成品の一つ”として供され、すりごまや味噌などの和え衣の味をまとわせることが重要です。
この違いを理解することで、スーパーでの買い物のときにも「何に使うか」をすぐに推測できるようになります。
さらに、研究や学校の給食でも、健康的な食事を作るヒントが詰まっています。
おからは食物繊維が豊富で腸の働きを助け、白和えは豆腐由来のタンパク質とごまの栄養を同時に摂れる利点があります。
よく使われる場面を知っておくと、家庭でのメニュー作りも楽しくなります。
このセクションを読んでいるみなさんは、きっと「次の休日に家で両方を使って料理してみたい」と思うでしょう。
実践に移す前に、以下のポイントを覚えておくと迷いが少なくなります。
・おからは食感が変わりやすいので、調理時間を短くするか長くするかで仕上がりが変わる。
・白和えは衣の味付け次第で野菜の風味が決まる。
・栄養価は両者とも高いが、特におからは繊維が多い点が特徴。
・保存方法はそれぞれ異なり、混ぜ物を増やすと風味が変わりやすい。
このように、同じ大豆由来の食材でも使い方が大きく違うのです。
材料・食感・用途の違い
原材料の観点から見てみましょう。
おからは絞りかすそのものが材料です。
袋の中に粉状の粒が細かく混ざっていることが多く、触ると微妙にザラつく感触があります。
味は淡く、塩味やしょうゆ味、だしを効かせると相性が良いです。
一方、白和えは豆腐が主材料で、そこにすりごまと味噌、砂糖、出汁などを混ぜた衣が加わります。
野菜と和えるときは、野菜の水分を軽く絞ってから和えると、味が衣に絡みやすくなります。
食感の違いも大きなポイントです。
おからは粒が細かく、しっとりとした口当たりから、時には軽く崩れやすいイメージがあります。
白和えは衣が滑らかで、豆腐の柔らかさとごまの香りが口の中で広がります。
用途も違います。
おからはサラダのトッピング、炒め物の食感づけ、卵焼き風の具、煮物のつなぎなど、様々な料理の材料になります。
白和えは副菜としての定番で、野菜をやさしく包み込む役割を果たします。
栄養面も違います。
おからは食物繊維が豊富で腸にやさしく、満腹感を得やすい特徴があります。
白和えは豆腐由来のタンパク質を摂取でき、体を作る元になる栄養素が含まれています。
保存方法も違い、乾燥させて粉末状にしたおからは長期保存がしやすい一方、白和えは作りたての美味しさを保つため、なるべく早めに食べ切るのが良いです。
このように、材料・食感・用途・栄養・保存の5つのポイントを押さえると、どちらをどんな場面で使うかが自然と見えてきます。
次の表では、簡単に違いを比較してみましょう。
表を見れば、同じ大豆由来でも用途や味の方向性が大きく違うことが一目で分かります。
こうした違いを理解しておくと、家族や友達と料理を作るときに「今日はどっちの素材を使って何を作ろうか」と会話が弾むことでしょう。
最後にもう少し実践的なヒントを紹介します。
・おからは水分をよく切ってから使うと、味が染み込みやすい。
・白和えは野菜を切る前に塩もみして水分を抜くと、衣がすっきりまとまる。
・両方とも冷蔵庫で保存する場合は、風味の変化に注意して早めに使い切る。
・子どもと一緒に作るときは、砕いたごまで香ばしさを足すと食欲を刺激しやすい。
この知識を土台に、次の家庭の献立におからと白和えを組み合わせてみてください。
友達との雑談でよくある話題を深掘りしてみると、おからの魅力は思ったより複雑だと気づく。私は体育の後の腹ペコタイムに母がよくおからの煮物を作ってくれた。豆の香りと野菜のシャキシャキ感、そしておからの繊維の満腹感が、次の授業の集中力を保つコツになったんだ。おからはただのカスではなく、調理次第で栄養価と食感を自在に操れる“万能食材”だと感じる。私は友だちにも、白和えのごま団子のような香ばしい風味と豆腐の柔らかさの組み合わせを伝え、味の組み立てを一緒に楽しむことが多い。日常の中で、食品ロスを減らす取り組みとしてもおからは優秀。煮物のつなぎやサラダの食感づけに使うと、少量でも満足感が得られる。さらには、子どもにも理解しやすい料理教育としての役割もある。食材の違いを知ることは、味だけでなく、栄養、調理法、そして食文化への理解を深める第一歩になる。