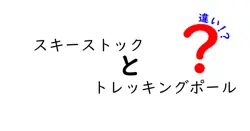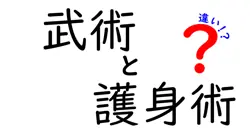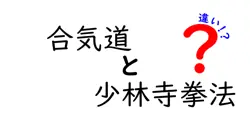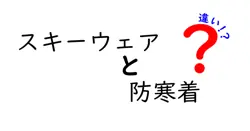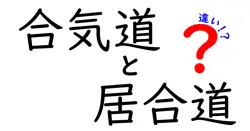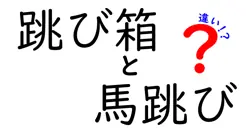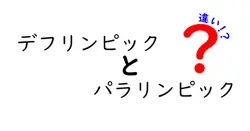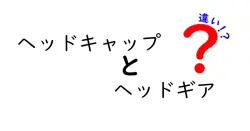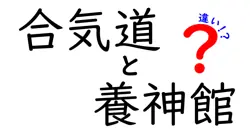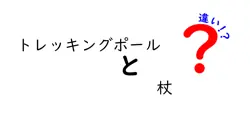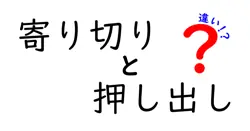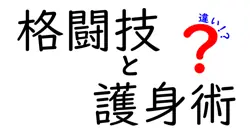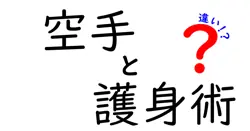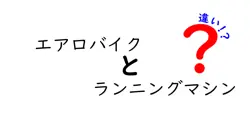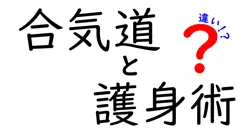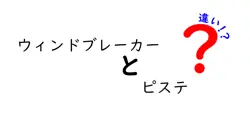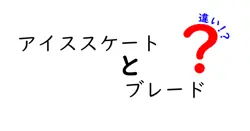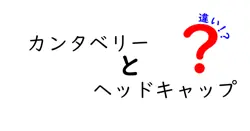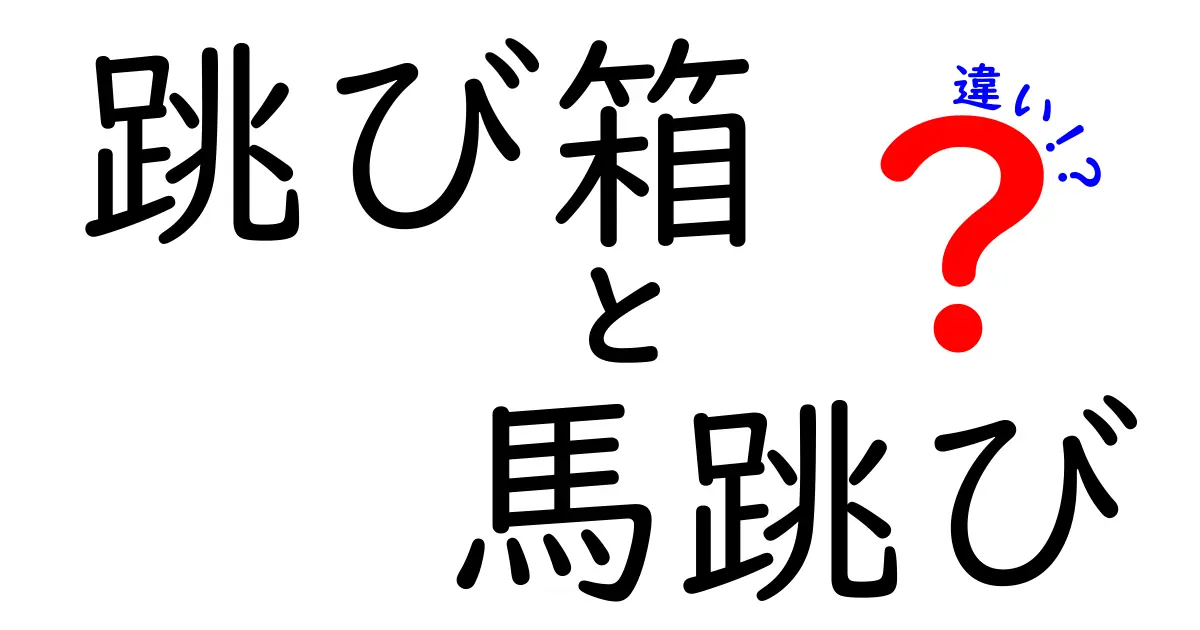

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
跳び箱と馬跳びの違いを徹底解説!中学生にも伝わる安全とコツの正しい選び方
このブログ記事では、体育の授業でよく出てくる“跳び箱”と“馬跳び”の違いを、初心者にも分かりやすく整理します。まず基本を押さえると、跳び箱は長方形の箱状の道具で、床と箱の間にクッションマットを敷いて前方へ跳ぶ練習が中心です。高さは複数段あり、子どもから大人まで段階的に練習できます。跳ぶ動作は“踏み切り”と呼ばれる助走の力を箱へ伝え、体を伸ばして越えるのが特徴です。対して馬跳びは、木製の“馬”の上をまたいで越える運動で、主に横方向への跳躍と体のひねりを必要とします。馬跳びは比較的小さな助走で始めることが多く、足をそろえて前方に跳ぶことが多いです。これら二つの種目は目的や難易度、必要な技術が異なるため、授業の段階や成長段階に応じて適切な練習計画を立てることが大切です。特に初心者は、安全第一を最優先に、壁やマットの安全距離を確保し、コーチの指示に従いながら進めましょう。これから詳しく、道具の違い、練習の組み方、そして怪我予防のポイントを丁寧に解説します。まずは全体像を掴み、次の段階へ進む準備を整えましょう。
なお、本稿は中学生のみなさんが理解しやすいよう、難しい専門用語を避け、日常的な動作に置き換えて説明しています。強調したい点は跳び箱は高さを使う道具であること、そして馬跳びは体の柔軟性と正確な着地の技術が問われることです。両方とも、練習を重ねることで身体のコントロール力が高まり、スポーツ全般の動作にも良い影響を与えます。
ここから先、道具の特徴と練習の組み方、そして安全対策を順番に詳しく見ていきます。まずは道具の違いを理解し、次に実践のコツ、そして安全面の配慮へと入ります。各節は具体的なポイントを押さえて作成していますので、授業の準備ノートとしても活用できます。特に着地の安定性と助走の長さの調整は、怪我を防ぐための最重要点です。今後の練習プランを立てる際には、児童の体力や柔軟性、運動経験を考慮して、段階的に難易度を上げていくことをおすすめします。
基本情報と違いの整理
跳び箱は箱状の道具で、複数段の高さを設定して跳ぶ練習を中心に行います。助走をつけて踏み切り、体を前方へ引き上げながら箱の上方へ越える動作が基本です。跳び箱の練習では、主に「高さの選び方」「踏み切りの角度」「着地の安定性」が重要ポイントとなります。高さを段階的に上げることで、体幹の安定性と股関節の柔軟性、膝の衝撃吸収能力を高められます。馬跳びは木製の馬を越える運動で、跳ぶ動作は横方向に近い動きが多く、体をまっすぐ保つ意識と着地の正確さが求められます。馬跳びの練習では、視線の位置、腰の位置、膝の曲げ具合など、細かな点が着地の正確さに直結します。これらの違いを理解することで、同じ体育の時間でも生徒一人ひとりに適した練習メニューを組むことが可能になります。
道具の形状と使い方の違いを把握すると、学習の順序も見えてきます。跳び箱は段階的な高さ設定ができるため、初心者は低い段から始め、段を一つずつクリアしていく過程で自信と技術を築いていきます。一方、馬跳びは初動の助走距離を短く設定して、着地のリズムと体のバランスを身につけることが重要です。このような理由から、跳び箱は「高さを使う技術」を磨く訓練、馬跳びは「連続動作と体幹の安定性」を養う訓練として、それぞれの特性に合わせたカリキュラム設計が求められます。最後に、授業での安全管理の実践として、コーチや先生の指示に従い、器具の状態を常に確認すること、着地時の膝の柔軟性を保つこと、適切なマットの配置を徹底することを強調します。
このセクションの要点を簡潔にまとめると、跳び箱は高さを活用する跳躍の技術、馬跳びは体の連携と柔軟性を要する技術である、という点に集約されます。
実践のコツと安全対策
安全対策の基本は、正しいフォームと適切な準備体操から始まります。跳び箱の場合、箱の高さは生徒の技術レベルに合わせ、初めは低い段から練習します。着地の安定性を最優先にし、着地時の膝を柔らかく使い、手は前方へつくか、横へ前方へ置くことで転倒を防ぎます。馬跳びでは、跳ぶ前に視線を前方へ向け、腰を低く保つ、両足をそろえて跳ぶことを意識します。いずれの種目も、初動の助走の長さを誤ると着地位置がずれ、怪我の原因になります。安全のための道具点検も欠かせません。マットの厚さ・反発、馬の滑り止め、踏み切り台の安定感を確認し、摩耗している箇所は即座に交換します。練習メニューとしては、段階的な難易度の組み合わせが効果的です。例として、跳び箱は低い段→高さを1段ずつ上げる、馬跳びは横跳び練習→前跳びへつなげる、というように、徐々に技術を積み上げていきます。生徒同士での安全確認の声掛けも大切で、誰かが苦手な動作をしているときはペアを替える、見守り役を設けるなどの工夫が必要です。
以下は短期的な練習プランの例です。まずは、基礎的な体づくりとして股関節周りの柔軟性を高めるストレッチを毎日行います。次に跳び箱は低い段を使い、踏み切りの角度と着地の安定性をチェックします。馬跳びは、横跳びの正確さと着地時の体幹の姿勢を重視してメニューを組みます。最後に、両技を組み合わせたミニセッションを取り入れ、運動連携の自然な流れを作ります。適切な休憩と水分補給を忘れず、疲労が蓄積していると感じた時点で練習を中止する判断も重要です。
練習メニューの例と表
以下は短期的な練習プランの例です。実際には学校の時間割や生徒の体力に合わせて微調整してください。
表では、跳び箱と馬跳びの主な目的、準備運動、難易度の上げ方、怪我のリスクを対比させています。生徒の安全を最優先に考え、練習の前後には必ず安全確認を行ってください。
| 項目 | 跳び箱 | 馬跳び |
|---|---|---|
| 主な目的 | 高さを使った跳躍の練習 | 体の横移動と着地の正確さ |
| 準備運動 | 股関節の柔軟性、膝の屈伸 | 腰回りの柔軟性、体幹の安定 |
| 難易度の上げ方 | 段を1段ずつ増やす | 距離を長く、跳ぶ距離を伸ばす |
| 怪我のリスク | 着地時の膝 | 腰・背中の過度な反り |
この表を活用して、授業の進行ペースを決めると効果的です。生徒の反応を見ながら、次の段階へ進むかどうかを判断してください。安全と成長を両立させることが、体育の授業で最も大切な目標です。
友達Aと友達Bが体育館の跳び箱と馬跳びについておしゃべりをしています。友達Aは跳び箱の高さを上げるときのコツを熱心に話し、友達Bは馬跳びの着地の正確さと腰の位置を大切にするポイントを深く掘り下げます。二人は“高さを使う技術”と“体幹を整える技術”の違いを実演を交えて分かりやすく説明し合い、授業ノート用に自分たちの練習計画をメモ。結局、どちらの種目も練習を積むほど上手くなること、そして安全第一で取り組むことが大切だと納得します。途中でコーチが現れ、道具の点検と適切な休憩の取り方をアドバイス。こうした会話の中で、跳び箱と馬跳びの違いが自然と身につく様子が描かれています。