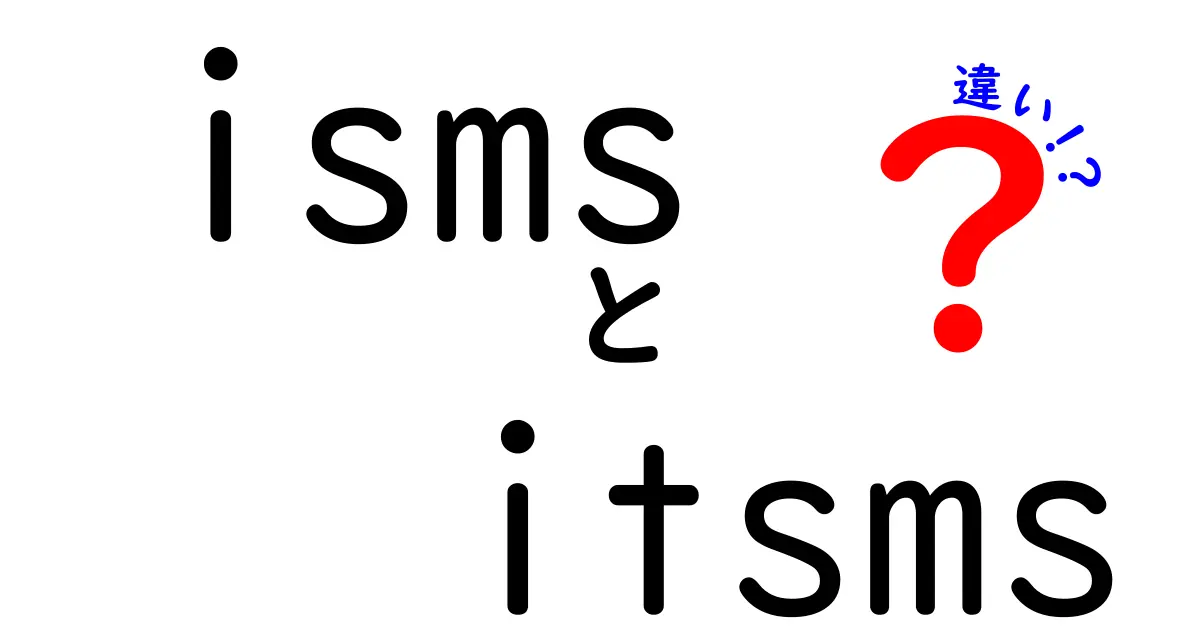

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:ismsとITSMsの違いを理解して混乱を解く
この話題は最初は混乱しやすいポイントです。ismsとは英語の接尾語で、 信念・思想・価値観 を指す言葉の総称として使われます。資本主義/社会主義/自然保護主義/フェミニズムなど、世界で広く語られる考え方の集合を表します。対して ITSMsは Information Technology Service Management の略で、情報技術の「サービス提供や運用」を組織として整えるための仕組みを指します。つまり、前者は社会や文化の観点の概念・信念、後者はITの運用を管理する実務体系という、全く別の領域を表す言葉です。
この二つは音が似ているだけで、用途も目的もまったく違います。
例えば、▲ある人が「環境保護を進めるべきだ」と信じる理由はその人の isms に基づく価値観です。一方で、IT部門が「システム停止を減らすために変更管理を厳格にする」と決めるのは ITSMs の実務的な取り組みです。
このように、使われる場面と意味が異なることを覚えるのがコツです。
本稿では、ismsと ITSMs の違いを中学生にも分かる言葉で丁寧に解説します。
長い文章になりがちですが、要点を押さえれば混乱はすぐに解けます。
これからの章では、意味の違い、具体的な使い方の違い、そして実務での活用例を順を追って紹介します。
難しく考えず、身近な例と比べながら読み進めてください。
ismsとITSMsの基本的な意味を分けて覚えよう
まずは両者の基本的な意味を分けて整理します。
isms は「系統・思想・信念の集合」を表す語であり、特定の社会的・倫理的な立場を指し示すことが多いです。例としては「資本主義isms」「フェミニズムisms」などが挙げられ、それぞれの立場には賛否両論がつきまといます。これらは世界の考え方のグループであり、価値観の話題や歴史・文化の背景と深く結びつきます。
一方で ITSMs は「情報技術のサービスを安定的に提供するための管理手法・枠組み」を指します。ITサービスの品質・信頼性・効率性を高めることを目的とした実務的活動であり、インシデント対応・変更管理・サービスレベルの監視など、具体的な業務プロセスが中心です。
つまり、isms は“何を信じるか”という思想的な話、ITSMs は“どう運用するか”という運用面の話、という大きな分かれ目があります。
この二つを混同すると、議論の焦点が見えなくなることが多いので、常に「これは信念の話か、それともITの運用の話か」を意識すると整理しやすいです。
具体例で比べてみよう
違いを実感するために、身近な具体例で比べてみましょう。
例として「ある学校が環境保全を推進するにはどうするべきか」という問いと「企業のIT部門が新しい監視ソフトを導入するべきか」という問いを並べて考えます。
環境保全を推す理由はismsに基づく信念の話であり、倫理・社会の価値観・社会全体の将来像が関係します。人によっては「経済的なコストがかかる」という現実的な反対意見も出るでしょう。そこで学校は、学期の方針・教育カリキュラム・地域社会の期待などを総合してどの価値を優先するかを決定します。これが ism 的な判断です。
一方、IT部門のケースでは、変更管理プロセスを導入して新しい監視ソフトのリスクを評価し、インシデントの発生を最小化するための手順を整えます。これはITSMs 的な判断であり、「どう動かすか」という運用の話です。
このように、同じ“決定をする”行為でも、背景にあるものが異なると結論の出し方や評価指標も変わってくることが分かります。
この表を見れば、どのような話題が“思想的”か“技術的”かを一目で判断できます。
また、実務においては ITSMs は標準化された手法(例:ITIL や ISO/IEC 20000 など)に基づく運用の改善を目指すのが特徴です。対して、isms は特定の組織・社会の価値観を説明・比較・検討する際の枠組みとなります。
つまり、ある話題を議論するときは「これは信念の話か、運用の話か」を最初に識別するだけで、整理の手順がぐっと楽になります。
まとめ:混乱を避けるコツと使い分けのポイント
これまでの話をおさらいします。
isms は 「信念・思想・価値観の集合」、ITSMs は 「ITサービスを運用・改善するための管理枠組み」です。
使い分けのポイントは、話題の“領域”と“目的”を見分けること。
身近な場面では、哲学的・社会的な議論にはisms、IT部門の運用改善にはITSMsという具合に、区別して扱うと理解が速くなります。
この考え方を覚えておけば、将来大人になってビジネスの場面に出会っても、混乱せずに適切な用語を選べるようになります。
最後に覚えておきたいのは、「似た音・似た形の言葉でも意味が大きく異なる」という基本ルールです。
このルールさえ意識すれば、これからも用語の混同を減らせます。
友人のミカと私は、学校の文化祭の準備をしているときのことを話していました。私が「ismsって、要するに“信念の集まり”だよね」と言うと、ミカはすぐに首をかしげました。彼女はIT部門で働くことを夢見ており、私の話をITSMsの話に引き寄せてきたのです。彼女は「ITSMsはITサービスを安定させるためのやり方のことだよ」と教えてくれました。私たちは混乱しながらも、ismとITSMsの違いを対比表にまとめてみることにしました。会話の中で、環境保護を推す理由はismsの価値観に基づく話だという点を確認し、IT部門の変更管理はITSMsの実務の話だという点を実例として確認しました。その日のノートには、「信念と運用は別物」という結論と、混同を避けるための識別基準がしっかりと刻まれていました。こうした日常の会話からも、用語の違いを深く知ることができると実感しました。





















