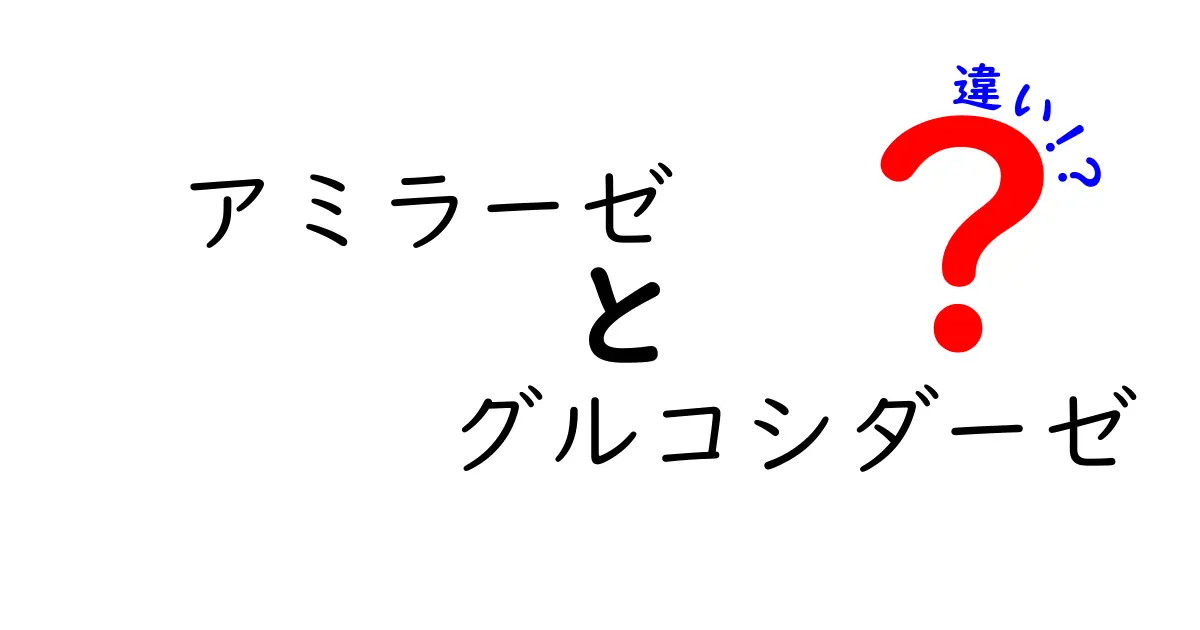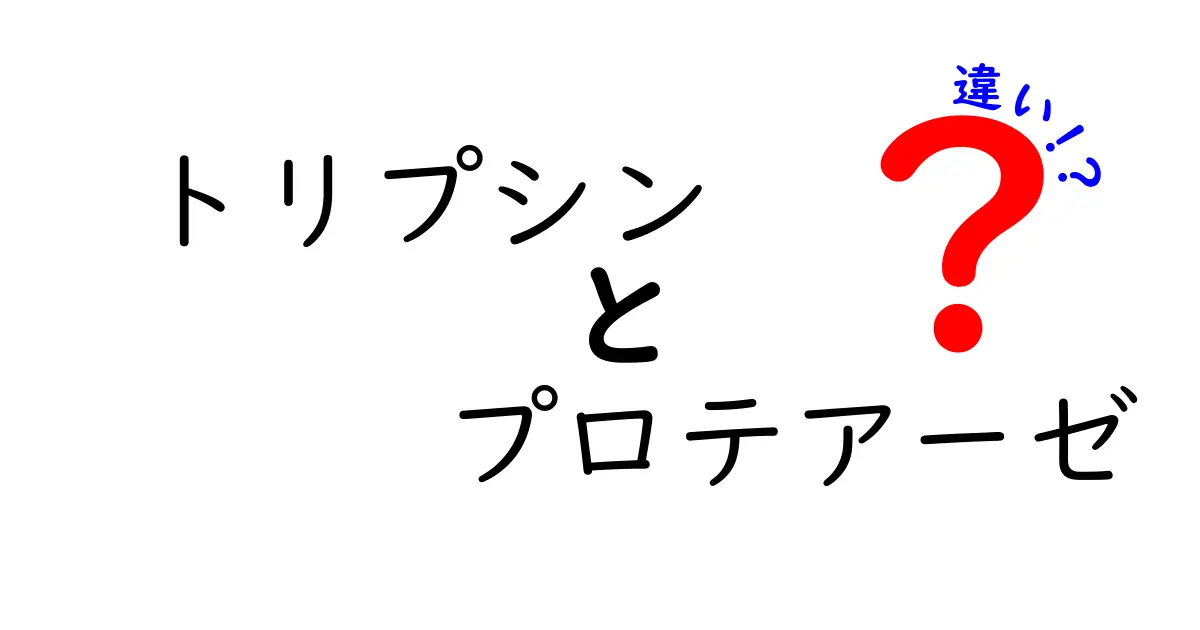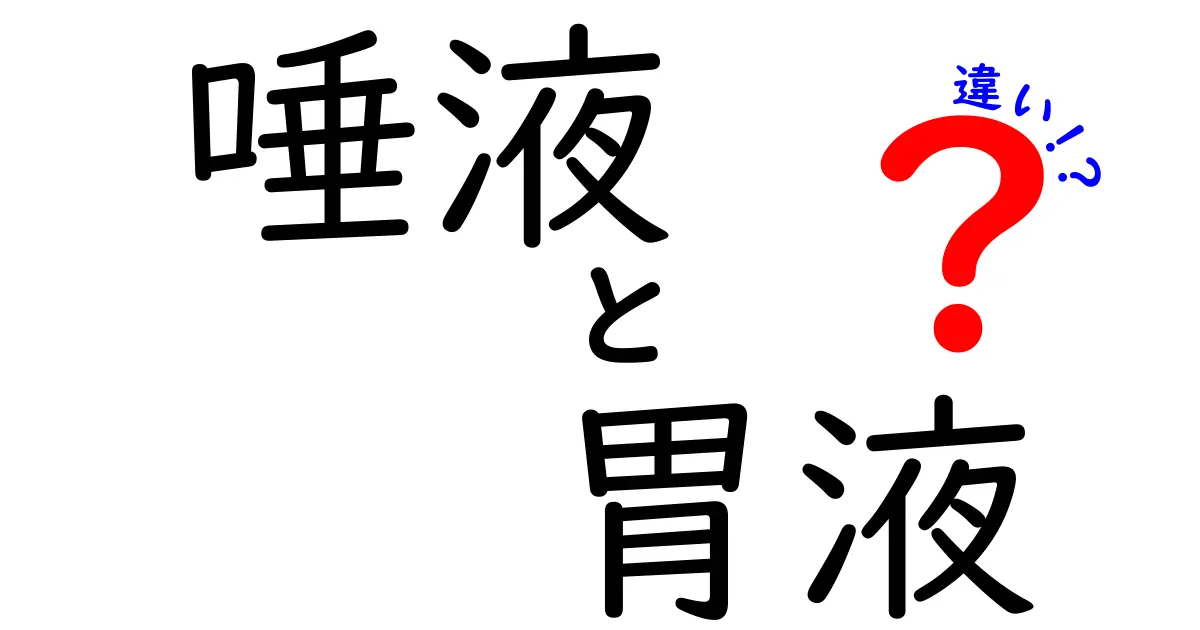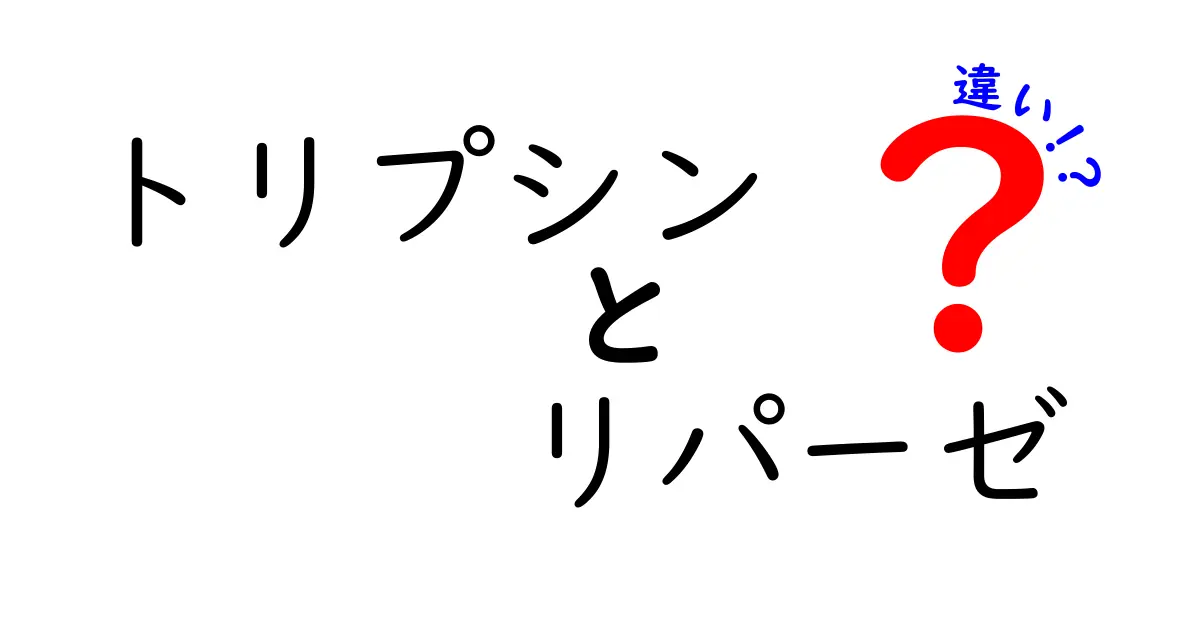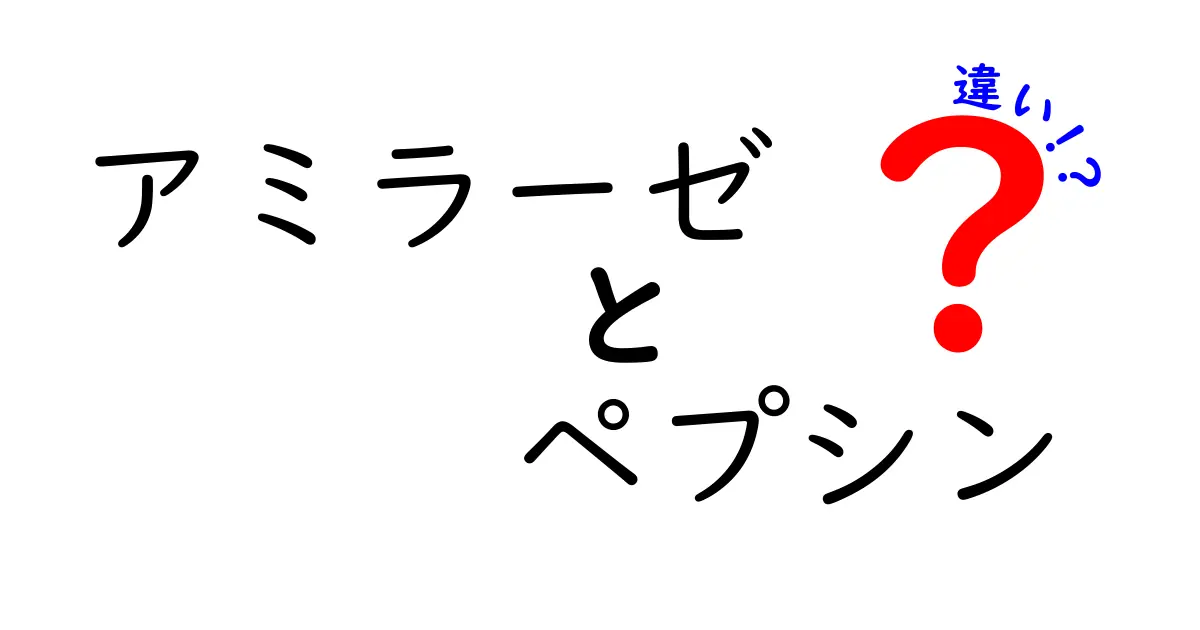

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
アミラーゼとペプシンの基本的な役割と違い
食べ物が体の中でどう分解されるかを考えるとき、まず思い浮かぶのがアミラーゼとペプシンという二つの酵素です。
アミラーゼはデンプンといった糖の大きな塊を、マルトースやデキストリンといった小さな糖に分解します。これに対してペプシンはタンパク質を小さな断片、ペプチドへと崩します。
つまり目的物と働く場所が違うという大きな違いがあるのです。
アミラーゼには唾液腺から出る唾液アミラーゼと膵臓から出る膵臓アミラーゼの二つがあり、口の中と小腸の途中で連携して働きます。唾液アミラーゼは口の中でデンプンをある程度分解しますが、食べ物が胃へ届くと胃酸の影響で活性が落ちます。膵臓アミラーゼは小腸に入ってから粘液の中を進んでデンプンをさらに分解します。ペプシンは胃で活躍します。胃は強い酸性条件で、ペプシノゲンという前駆体が酸の力でペプシンへと変身します。活性化したペプシンはタンパク質の特定の結合を切って、長いタンパク質を短い断片へと切り分けます。こうして体は最初の段階でデンプンとタンパク質を別々の小さな部品にしてから、腸の中でそれぞれが必要な栄養として吸収される準備をします。
この二つの違いを覚えるコツは一言で言えば役割と場所の違いです。アミラーゼは糖を分解し、ペプシンはタンパク質を分解するという別の目的を持つ酵素です。デンプンをマルトースへ分解、タンパク質をペプチドへ分解という言葉をセットで覚えると理解が進みます。口の中と胃、そして腸の中でどう連携して進むのかを思い浮かべてください。
アミラーゼとペプシンの違いを比べる表で理解を深めよう
ここからは違いを見た目で理解できるように簡易表と補足説明を用意しました。次の表は役割、場所、基質、最適pH、活性化の仕組み、そして最終的な生成物をまとめたものです。理解を深めるためにも表をじっくり見てください。
下の表は生活の中でのイメージをつかみやすくする助けにもなります。
日常の食事の場面を思い浮かべると、パンをかじるときの口の中の反応や、肉を食べて胃が酸性環境になってタンパク質分解が始まる様子が見えてきます。
ねえ、アミラーゼとペプシンの話を雑談風にすると眠くならないよね。実はこの二つの酵素はそれぞれ違う相棒みたいなもの。口の中で働くアミラーゼはデンプンの最初の一歩を踏み出し、胃に到着すると酸で活性が抑えられ、代わりに腸で働く別のアミラーゼが活躍する。ペプシンは胃でタンパク質を分解する役割を担い、連携して体は栄養を取り込みやすい形に整える。こうした仕組みを知ると食事の時の驚きが減り、授業で出てくる話題にも自信がつく。
前の記事: « 宿便と脂肪便の違いを徹底解説|知っておくべき腸のサインと対策